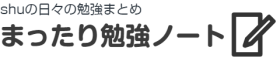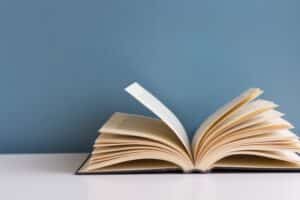基板から自作キーボードを作ったので自分も基板から作りたいと思った人へ
今回は初めて基板から自作キーボードを作りました。もともと基板から作る気はなかったのですが、同僚が「基板から作るのも難易度高くないですよ」とアドバイスしてくれて踏ん切りがついたので、挑戦しました。今回の記事はそんな基板から作る自作キーボードに初チャレンジする昔の自分のような人向けに、基板から作りたかったらどうすればいいのか?を紹介する記事になります。

目次
そもそもなぜ自作キーボードを基板から作ったか?
Youtubeでたまに自作キーボードの紹介を見て、自分も欲しくなったため、今年になっていくつか自作キーボードのキットを買って自作キーボードを作るということをしています。
ただ、自作キーボードのキットは個人が作っているものが多く、人気なキットは入手難易度が高い印象です。
例えば、roBaやmoNa2 などの無線+分割+トラックボールのような人気のキットは、開発者の方が結構定期的に在庫補充してくれている印象ですが、在庫が入ったら数分で売り切れてまったく買える気配がありません。
また、この手の小型の分割キーボードは「自分ならここにキーがほしい!」という要求が使っているといろいろでてきます。
そんなわけで5月か6月ごろから「もうこれは自分でつくるか」ということで基板から設計をすることにしました。
2025年8月現在、基板から自作キーボードを作りたくなったらどうすればいいか?
自作キーボードに何を求めるか?で大分話が変わりますが、自分は以下のような要素がほしくて自作キーボードを作りました。
- 分割キーボード
- 完全無線(分割キーボード間も無線だし、PCとキーボードの間も無線)
- 最低片側6カラム、合計12カラム
- トラックボールあり(できればスクロールとカーソル操作を別々のボールで操作したいので二つ)
自分と同じような要素を盛り込もうと思った場合、実は2025年8月現在はnoteで最高の資料が公開されています。
それが先ほど紹介したmoNa2を開発している白湯さんが書いたnoteの記事になります。
https://note.com/pooh_polo/m/me4a885480f75
このnoteのマガジンの記事では無線分割キーボードであるTweakbitというキーボードを作る流れなどが紹介されています。一部有料記事ではあるりますが、すごく安い+キーボードを基板から自作した場合にかかる費用からすると誤差みたいな金額です。
このため、キーボードを作りたいと思った場合、現在なら有料記事も含めて全部1読することがまず1歩かと思います。
それ以外の要素のキーボードを作りたいときの参考になりそうな資料は?
要素ごとに参考になりそうな資料が微妙に違うのでカテゴリーわけして紹介していきます。一部重複する資料があります。
Tweakbitからレイアウトを変えたい
写真を見ればわかりますが、Tweakbitは格子状にスイッチを配置するオーソリニア配列です。これは基板から作る場合、作成の難易度が下がるので初心者向けのキーボードとしては作りやすくてよいのですが、ここを変えたいという要求がまずでてくると思います。
この場合、スイッチのレイアウトを事前に考えてからキーボードの基板を作るという流れになると思います。この辺の流れは以下の本が一番詳しく載っていました
- 自作キーボード設計入門(電子版) (https://booth.pm/ja/items/1044084)
ケースにこだわりたい
同じ基板でもケースが違うと印象がガラリと変わります。このため、ケースにこだわりたいという要求は出てくると思います。その場合はこちらの本がお勧めです。
- 自作キーボード設計ガイド Vol2 ケース設計編 (https://salicylic-acid3.booth.pm/items/4982088)
Lipoバッテリーが怖いので有線にしたい
無線のキーボード向けのマイコンでよく使われるのはSeeed XIAO BLE nRF52840なのですが、多くの場合Lipoバッテリーが使われます。これは万が一を考えると火事の原因になりえるので、怖いということを考えます。この場合は以下の資料がお勧めです。
- 自作キーボード設計入門(電子版) (https://booth.pm/ja/items/1044084)
- 自作キーボード設計入門2(電子版) (https://booth.pm/ja/items/1315935)
注意点としては2025/8現在、公開されているサンプルが少し違うなどの問題があるので、適宜現状に合わせて読み替える必要があります。
初心者が基板から自作キーボードを作る際の注意点
注意点としては以下の二つです
- 2025年8月から大分あとの場合、いろいろ情報が古くなっている可能性がある
- 自分が盛り込みたい要素がTweakbitと違う部分がある場合、この記事の情報だけでは実現できない場合がある
まず1についてです。これはもうどうしようもないと思いますが、情報が古くなった場合、例えばツールの使い方が変わっていて、初めて触る人は苦労するみたいなことが発生する可能性があります。
例えば、基板の設計時に使われるKiCadや3D CADのFusionはちょっと前の資料と今とで使い方が変わっている部分がありました。このような変化はある程度知識がある人にとっては特に問題ないことが多いと思いますが、初心者は苦労するポイントかと思います。
二つ目として白湯さんが題材にしているTweakbitと違う要素を盛り込みたいという場合です。例えばキー数は同じでキー配置を変えたいなどであればそれほど問題ないのですが、キー数を増やしたいは実は難易度がすごく上がります。
この話自体はnoteの記事に書かれていますが、Seeed XIAO BLE nRF52840というマイコンを使って、かつトラックボールありだと、普通にやったらTweakbitと同じキー数が限界になります。いろいろ裏技はあるので、増やせないことはないのですが、難易度は高くなると思います。
このようにキーボードに盛り込みたい要素に応じて難易度が変わるので、この点は注意してどのようなキーボードを作るか考える必要があります。
基板から自作キーボードを作る際の苦労ポイント
どの辺が大変なのかわかると参考になると思ったので、基板から作ることが初めての自分がどこに苦労したのか紹介しておこうと思います。
1. キースイッチとトラックボールのレイアウトの試行錯誤に時間がかかった
多分一番時間がかかったのがこの部分です。実は当初は全く知識がなかった基板の設計に一番時間がかかるのでは?と思ってたのですが、基板の設計は実は数時間できました。一方、予想よりもはるかに時間がかかったのがこのキースイッチとトラックボールのレイアウトです。
予想ではこの部分は自分が今使っている「KeyBall」シリーズを参考にして変えるつもりがほとんどなかったので、すぐ終わると思っていました。
ただ蓋をあけると、KeyBallとキー数が違うので、その部分の調整をしていたら、いろいろ調整したくなり、3D プリンターで試作をしていたら、だんだんトラックボールの位置を変えたくなり、調整してたら思った以上に時間がかかりました。
おそらく自分はキースイッチのレイアウトにある程度要望があったため、この部分に時間がかかったと思われるので、盛り込みたい要素の部分に時間がかかるのを覚悟するのが良いかともいます。
2. ファームウェアの調整に時間かかった
これは基板から作らない自作キーボードでもある程度時間がかかるところですが、できたキーボードのキーマップやトラックボールの設定に結構時間がかかりました。
普通の自作キーボードの場合、開発者の方が練りこんだキーマップをデフォルトにしてくれているおかげで、ユーザーは結構キーマップ作製の時間短縮ができる印象ですが、基板から作るとなると、参考にするキーマップがないので、いろいろ考えて結局時間がかかるということがありました。
トラックボールに関しても同様で、感度をいろいろ調整するのに時間がかかった印象があります。
終わりに
今回は基板から自作キーボードを作ったので、自分と同じように基板から作ってみたいと思っている人向けに記事を書いてみました。
この記事を見て「自分もできそう!」と思ってもらえれば幸いです。